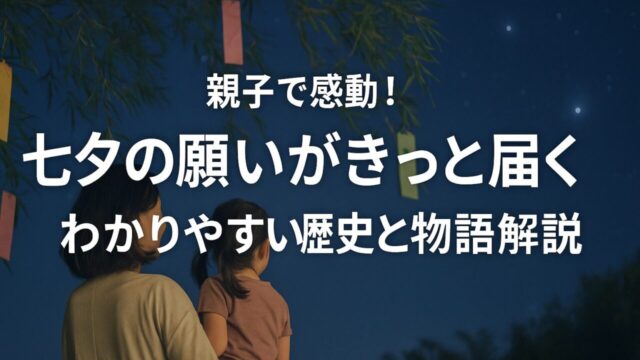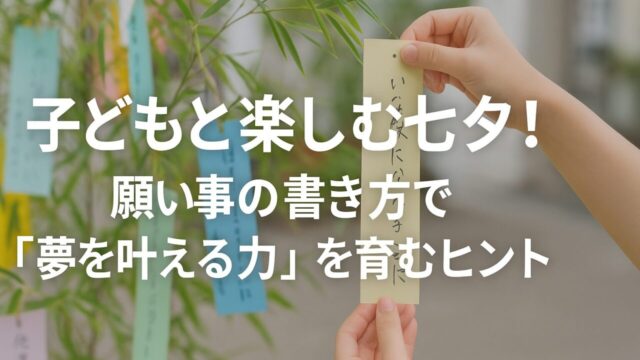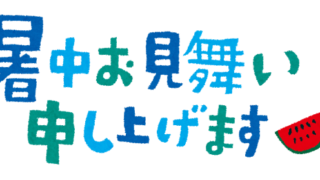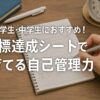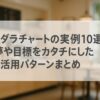今回は、七夕飾りの一つである「巾着(きんちゃく)」の作り方をご紹介します。七夕飾りにはそれぞれ意味が込められていますが、巾着には一体どんな願いが込められているのでしょうか?
七夕飾り「巾着」について知ろう
巾着とは?その由来と意味

(参考:みちのく旅日記)
昔は腰からぶら下げてお金を入れていた巾着。現在でもファッションアイテムとして使われることがありますね。
七夕祭りには七つの飾りがあり、その一つである巾着には商売繁盛の願いが込められています。口をきちんと結ぶことで浪費をしないようにと戒める意味も持ち合わせています。七夕飾りに使う際は、主に「紙衣(かみごろも)」と一緒に飾られます。
—
巾着飾りを作ってみよう!
用意するもの
- 包装紙やチラシ
- 針と糸
- 両面テープ(またはのり)
用紙が小さいと細工がしづらいので、初めて作る際は大きめのものを使うのがおすすめです。お祭りで使われる巾着は和紙で作られています。慣れてきたら、小さめの和紙で挑戦してみるのも良いでしょう。
作り方
△行程2 黒い部分を切ります
- 長方形の包装紙を半分に切ります。(それぞれをAとBとします)
- Aは巾着本体に使います。半分に折り、折った部分の端を丸く切り落とします。ここが巾着の底になる部分なので、形を工夫してみてください。
端を整えたら、折り目の部分から切り離して一度ばらばらにします。(それぞれをAとA’とします) - 続いてBをさらに4分割ほどに切り分け、それぞれを半分に折って、周りに付けるヒダを作ります。半分に折ることで強度が増し、形が崩れにくくなります。
本来、ヒダの部分は巾着と同じ紙ではなく、お金に縁があるようにと金紙や銀紙を用いることがあります。こだわりたい方は色を変えてみてください。 - 巾着Aの縁に両面テープやのりをつけてヒダを貼っていきます。途中でヒダの目の向きを変えてみても面白いでしょう。余った部分はハサミで切ります。
貼り終えたらヒダを挟むように巾着A’をくっつけて袋状にします。 - 最後に巾着全体の形を整えるためにタックを作りましょう。中に紙くずを詰めて膨らませ、口を糸で縛れば完成です。
余った紙でリボンをつけると、さらに可愛くなりますよ。
—
七夕の豆知識:七夕の由来を深掘り
七夕と書いて「たなばた」と読むのはなぜでしょうか?その由来には諸説ありますが、「棚機(たなばた)」「織女星(しょくじょせい)と牽牛星(けんぎゅうせい)」「乞巧奠(きこうでん)」の三つが合わさったものだと言われています。
棚機(たなばた)
棚機は日本に伝わる古い習わしで、選ばれた乙女が水辺の機屋にこもり、豊作を祈って神様へ着物を織り捧げました。後に仏教が伝わり、お盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるように変わっていきました。そのときに使われていた織り機が「棚機」です。
織女星と牽牛星の伝説、そして乞巧奠
織女星と牽牛星の伝説は、多くの方がご存知でしょう。中国では、裁縫を司るベガ(織女星)と農業を司るアルタイル(牽牛星)が旧暦の7月7日に最も輝きを増すことから、年に一度の巡り合いの日だと考えられました。この日、庭先にお供え物をして裁縫や書道などの上達を祈る行事を乞巧奠(きこうでん)と呼び、これが日本に伝わったと言われています。
—
他にも七夕関連の情報に興味がある方は、こちらの記事もおすすめです↓↓