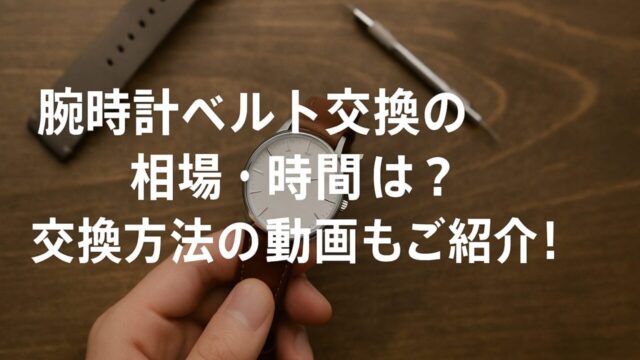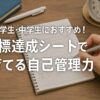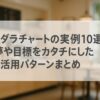アロマは香り(人にとってのよい匂い)を意味しますから、
「虫よけ」と「アロマ」とを組み合わせると、「よい香りの虫除け」ということになります。
そこで思いつくのは、ハーブです。
例えば、ペパーミントの香りは人に心地よく、虫にとっては大嫌いな臭いだからです。
虫よけにアロマ?スプレー?
虫よけにペパーミントを用いるとして、それを、
アロマテラピーの手法(ここでは単にアロマといいます)で用いるか、
それともスプレーで用いるか、というのがここでのテーマです。
アロマは、その香りが部屋全体に漂うので、使用を継続することで、
部屋の中の虫は全体的に部屋の外へ退散し、
同時に、人は良い香りの中で、精神の寛ぎを得ることができ、セラピー効果を期待できます。
スプレーは、スプレー液滴が特定部位へ集中的にかかるので、
虫が集中している場所にかかれば、虫の追い出しにとても有効に働くでしょうが、
別の場所にいる虫にはそれほどの効果がないでしょう。
また、スプレー液は蒸発が早いので臭い成分が短時間に消えてしまいます。
長時間、アロマの匂いの部屋にいるのが苦痛だという人にとっては、スプレーが適しているといえます。
そんなわけで、部屋の中の虫の分布状態に応じて、
アロマ、スプレーを使い分けがよいと思います。
なお、手作りスプレーは問題ないでしょうが、
過去に市販の虫除けスプレーに含まれた「ディート」という成分で
健康被害を起こした事例があったという話があり、気になるところです。

虫が嫌がるものとは
虫が嫌がるものは、ハーブの匂いです。
動物と違い、動けない植物は、
自己防衛のために虫が嫌がる臭い成分を生成する能力があり、
それで虫を撃退しているのです。ハーブを香りとして感じる人類は幸いです。
例えばペパーミントは、こばえ、蚊、ダニ、あぶ、ぶよ、ゴキブリ、
その他多くの虫に対し忌避効果があるといわれています。
[ad#ad-1]
虫よけアロマキャンドルの作り方
(材料)
注意:以下の材料は、アロマキャンドル作りの専用グッズとして用意し、他の用途に兼用しないことです。
用意するもの
ロウ(パラフィン又は密蝋)・・・作ろうとするキャンドルに合わせた適量。
密蝋:働き蜂の分泌物です。天然のアロマを作るならおすすめです。
パラフィン:石油精製工程で作られます。キャンドル用ペレットタイプがよいです。
芯と芯立て
手作りキャンドル用の芯と芯立て(芯立てはボタンで代用できます)
芯と芯立てのセットも販売されています。
湯せん用容器・・・作ろうとするキャンドルの量が十分入る大きさの耐熱容器。
ロウを流し込む耐熱ガラス容器=出来上がるキャンドル外壁になります。
作りたいキャンドルの数だけ用意します。
キャンドル作り専用の小鍋。湯せん容器を収容できる大きさのものを用意します。
お好みのアロマオイル(精油)・・・10~20滴
虫よけアロマとしては、ペパーミントのほか、
ゼラニウムやティトリーなども知られており、お好みに応じて選択してください。
10~20滴としましたが、パラフィン又は密蝋の3~5パーセントの比率が目安です。
軍手
キャンドルの製作工程で高温の鍋やロウを扱うので、手の保護に使います。
割り箸
※アロマオイルを除いて、100均のお店で間に合うと思います。
(手順)
軍手を着用して始めます。
工程1:芯立てに芯を取り付け、その芯立てを、5の耐熱ガラス容器の中心に置き、
芯の上端を割り箸で挟み、その割り箸をガラス容器の上縁に橋渡し状において芯が立つように安定させます。
工程2:3の湯せん用容器内に作るキャンドルの量に相当する量のロウを入れます。
工程3:小鍋内でロウを湯せん(※)で溶かします。
※湯せん=5の小鍋に3の湯せん用容器よりも少し浅い量で湯を沸かし、
その中に工程2の湯せん用容器を入れて、この湯せん用容器内のロウを溶かします。
工程4:湯せん用容器内で溶けたロウを、工程1で準備しておいた耐熱ガラス容器内に注ぎます。
工程5:粗熱がとれたら、アロマオイルを耐熱ガラス容器内のロウに注ぎ、冷めたら出来上がりです。
上記の耐熱ガラスから型抜きせずそのままアロマキャンドルとして使いますから、
芯から割り箸を外し、芯に点火してお使いください。
<注意点・ポイント>
虫よけアロマオイルとしては、有名なペパーミント、ハッカ油以外では、
レモンに似た香りのシトロネラや、レモンユーカリ、レモングラス、ゼラニウム、ラベンダーなどもあります。
アロマの焚きこめられた部屋にいて気分が悪くなるようならすぐに外に出て新鮮な空気を吸いましょう。
また、アロマキャンドルの消し忘れにご用心。
まとめ
好きな香りのアロマで虫よけできれば、アロマにより健康上の効果と合わせて一石二鳥で楽しいです。
手作りなら、好みのハーブを好みの強度で調整できます。